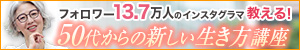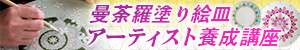6月は季節の変わり目。
梅雨に入り、自然が潤いを深めるときです。
そんな季節の移ろいを丁寧に伝えてくれるのが、「二十四節気」と「七十二候」。
二十四節気は、太陽の動きに基づき、一年を24等分した季節の指標のこと。
七十二候は、二十四節気をさらに約5日ずつに分けた暦です。
暦生活で、忙しい毎日に「日本の季節感」という静けさと彩りを取り入れてみませんか。
6月の二十四節気と七十二候 一覧と意味

6月の暦をご紹介します。
芒種(ぼうしゅ)(6月5日頃)
稲や麦など「芒(のぎ)」のある植物の種まきの時期をさします。
このころから、雨が増えてくることで知られています。
七十二候:
– 蟷螂生ず(かまきりしょうず):カマキリの子が孵化し始める
– 腐草蛍となる(くされたるくさほたるとなる):湿った草の下に蛍が光り出す
– 梅子黄なり(うめのみきなり):梅の実が黄色く熟してくる
夏至(げし)(6月21日頃)
昼の時間が一年で最も長くなる日です。
気温があがって、暑さが日に日に増す時期です。
七十二候:
– 乃東枯る(なつかれくさかる):靫草(うつぼぐさ)が枯れ始める
– 菖蒲華さく(あやめはなさく):菖蒲の花が咲き誇る頃
– 半夏生ず(はんげしょうず):半夏という草が生え始める、農作業の節目
暦生活の楽しみ方〜6月編〜

行事に積極的に参加したり、旬の食材を食事に取り入れたりすると、暦生活をより楽しむことができます。
季節の行事や風物詩を味わう
6月には、衣替え・梅仕事・紫陽花観賞・父の日などの行事があります。
季節の行事や風物詩をチェックし、参加してみませんか。
食で楽しむ
梅・らっきょう・鮎・新じゃが・青梅ジュースといった、旬の味覚を取り入れましょう。
「旬」をいただくことは、季節と自分をつなげる大切な行為です。
季節の言葉
手紙を書く時には、「入梅の候」「紫陽花の季節となりました」など、挨拶に季節感を取り入れてみましょう。
おわりに
現代は忙しく、せわしないけれど、暦に触れることで時間が優しく流れはじめます。
「今日はどんな日?」をスマホではなく、自然の言葉で感じてみるのも素敵ですよね。
皆さんも是非、日々の暮らしに暦を取り入れてみてください。