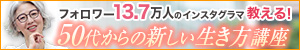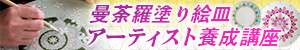「大祓」は日本の神道儀式で、毎年6月と12月に行われます。これは過去半年間の罪や穢れを祓い清めるための重要な儀式で、神々の前で無病息災と繁栄を祈り、心身ともに清浄になることを願います。
大祓の由来と目的

大祓は、特に神道の信仰において重要な役割を果たしてきました。宮中行事でも、祭祀の一環として神嘉殿の前で、皇族をはじめ国民のためにお祓いを行います。
儀式の主な目的は、罪や穢れを取り除くことで、神々の前で清らかな心と身体を保つことです。
大祓は年に2回
年に2回行われ、6月の大祓は「夏越(なごし)の祓」、12月の大祓は「年越の祓」と呼ばれています。
夏越しの大祓は、暑さや湿気で体調を崩しやすい時期に行われ、年越しの大祓は、1年を締めくくり、次の年に向けて心身をリセットする意味を持っています。
大祓の儀式と流れ

大祓では、大祓詞(おおはらえことば)を唱えて、「人形(ひとがた)」と呼ばれる人の形に切った白い紙などを使って、身についた半年間の穢れを祓います。
神社によっては、茅や藁を束ねた茅の輪(ちのわ)を神前に立てて、これをくぐることで穢れや災い、罪を祓い清めます。
神社によっては、茅の輪のくぐり方や順番が決められていることも。茅の輪の周囲に立て看板がないか、くぐる前に確認をしてくださいね。
人形(ひとがた)の納め方
人形(ひとがた)を納めて、神事でお祓いをうけましょう。
1) 人形(ひとがた)に名前と年齢もしくは生年月日を書きます
2) 人形(ひとがた)に息を吹きかけ、自身の穢れを人形にうつします
3) 人形(ひとがた)で、全身をなでます。痛い所や良くなって欲しい所は丁寧に
4) 人形(ひとがた)を袋に入れて、箱に納めます
おわりに
大祓は、罪や穢れを祓うとともに、自らを振り返るための機会としても大切な役割を果たします。大祓に参加して、半年の振り返りをしてみませんか。
大祓では、茅の輪をイメージしたお守りや、期間限定の御朱印を授与している神社も多くあるので、お出かけの際にチェックしてみてください。