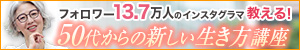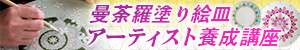災害はある日突然やってきます。
被害を最小限に抑えるには、日頃からの備えが鍵を握ります。
そこで本記事では、個人用の非常持出袋から家族向けの在宅避難セット、収納や点検の工夫まで、防災グッズの選び方をご紹介します。
これを機に、防災グッズの見直しをしませんか。
1人分の非常持出袋に必要な基本アイテム

災害発生直後、すぐに持ち出せる「非常持出袋」は命綱とも言える存在です。
飲料水・非常食は3日分を目安に準備
人は水がなければ3日も生きられません。
非常時に備えて、1日2〜3リットル、500mlペットボトル6本分を目安に水を準備しましょう。
食料は、調理不要で長期保存が可能な缶詰やレトルト、乾パンなどが便利です。
エネルギー補給を意識し、栄養補助食品なども活用しましょう。
トイレ・衛生用品・生理用品も忘れずに
避難所ではトイレ環境が整わないこともあります。携帯トイレやウェットティッシュ、消毒液などを備えておきましょう。
生理用品も多めに用意しておくと安心です。
ライト・バッテリー・情報収集ツールは必須
停電時の夜間活動や情報収集に備え、LEDライトやヘッドランプを用意しましょう。
予備電池やモバイルバッテリーもあわせて携行し、スマホの充電切れを防ぎます。
また、ソーラーパネルや手回しなど多彩な形で充電できるラジオ付きライがあると、情報と明かりを同時に確保できます。
現金と貴重品の防水管理も抜かりなく
災害時はキャッシュレス決済が使えない場合も。
小銭を含めた現金を準備し、防水袋に身分証や保険証、印鑑なども入れておきましょう。
必要な行政手続きや支援を受けるための身元確認に役立ちます。
家族みんなで備える自宅避難セット

自宅が安全な避難場所になるケースも少なくありません。
家族構成に応じて長期の在宅避難にも備えておきましょう。
家族全員分の水と食料を1週間分ストック
在宅避難を前提に、1人あたり1日2Lの水を7日分用意しましょう。
食料はレトルトやフリーズドライ食品を中心に、火を使わずに食べられるものを選びます。
缶詰を買い置きしておくのもおすすめです。
調理が必要な場合に備えて、カセットコンロやガスボンベも用意しておくと安心です。
子ども・高齢者向けのケアアイテムも用意
小さなお子さんがいる場合は、おむつや粉ミルク、おやつも多めに備えます。
高齢者には補聴器の電池、常備薬、老眼鏡などを忘れずに。
家族のライフステージに合わせて、必要な備えをリスト化しましょう。
日常使いできるアイテムで無駄なく備える
普段から使えるアイテムを防災グッズとして活用すれば、備えも無駄になりません。
たとえば、防災スリッパやポーチは、普段の暮らしにも取り入れやすい優秀な防災グッズです。
便利グッズと収納・点検の工夫
いざという時にすぐ取り出せるよう、収納方法や保管場所にも工夫が必要です。
多目的・軽量・コンパクトなグッズを選ぶ
ロープやビニールシート、ホウキなど、多機能な道具は災害時に大活躍します。
軽くて折りたためるアイテムを中心に選べば、収納や持ち出しもスムーズ。
使い方を日常から確認しておくと安心です。
外出先用の防災ポーチ・車載セットも便利
外出中に災害が起こった際にも対応できるよう、A5サイズのポーチに最低限の道具を入れて携帯しましょう。
車には応急セットや飲料水、保温シートを積んでおくと、帰宅困難時にも安心です。
定期的な点検と入れ替えを習慣に
防災グッズは「入れて終わり」ではありません。
年4回(3・6・9・12月)を目安に、賞味期限や電池の残量、グッズの劣化を確認しましょう。
ラベルをつけて分類収納すれば、誰でもすぐに使える状態に保てます。
食材は、賞味期限が切れる前に使って新しいものを補充しておきましょう。
災害に備えた「備え+知識+行動計画」

物資だけでなく、「どう行動するか」というシミュレーションも、災害対策には欠かせません。
家族で共有し、繰り返し訓練しましょう。
地域のリスクと避難ルートを家族で共有
まずは自宅周辺のハザードマップを確認し、災害リスクを把握しましょう。
避難所までのルートや所要時間を家族で確認し、実際に歩いてみることも大切です。
安否確認の方法と集合場所を事前に決める
災害時には連絡が取りづらくなることもあります。
あらかじめ「災害用伝言ダイヤル」や「LINEのノート機能」など、家族間の安否確認手段を決めておきましょう。
スマホが壊れたり充電が亡くなったりするケースを想定し、集合場所や連絡時の合言葉も設定しておくと混乱を避けられます。
非常持ち出し袋に、家族の連絡先を記入したメモを入れておくのもお忘れなく。
おわりに
防災は「備える」ことと「使いこなす」ことの両輪で成り立ちます。
また、一度揃えた防災グッズも、時間の経過とともに入れ替えや点検が必要です。
日常生活に取り入れながら、無理なく防災力を高めていきましょう。